第12回デビュー時代(2)
芸能界の大型エイリアン新人
- ——
- 前回からの続きで、サンディーさんが日本に腰を落ち着けて活動されるようになった70年代中頃の話です。
- Sandii
- はい。
- ——
- これまでも何度か同じ時代のお話を伺っていますが、毎回新ネタが登場する感じで新鮮なんですよね。
- Sandii
- 思い出がいっぱいあって記憶の底からどんどん出てくるのよ、その辺の話になると。あの頃は毎日毎日、目まぐるしく新しいイベントがあったから。
- ——
- では思い出サルベージという感じで、じっくり伺いたいと思います。その頃といえば、久しぶりにハワイから日本に帰っていらして、芸能の世界という新しい環境で吸収することが多かったのではないでしょうか。
- Sandii
- たしかに毎日何かしら重要なことが起きているような日々でした。
- ——
- それで前回の最後のお話では、当時NHKのディレクター/プロデューサーだった波田野鉱一郎さんの導きでサンディーさんがロックな世界に足を踏み入れていったと。
- Sandii
- そう。いつも言うけれど、波田野さんには大変お世話になりましたね。
- ——
- 当時の波田野さんは『新八犬伝』という当時NHKで放映されていた伝説的な人形劇の番組を担当された直後で、『新八犬伝』で黒子姿でナレーションを務めていらした坂本九さんと仲が良く、NHKのAM番組担当に復帰される際に「誰か英語もできるDJ向きのタレントさんはいない?」と尋ねたらサンディーさんが推薦されたと。
- Sandii
- だいたいそんなところですね。「若いこだま」のDJ担当は74年か75年の秋から始まったのは憶えています。

「若いこだま」生ライヴ中の写真。
ファンの方が送ってくださった当時のサンディー。
(photo by Takagi-san)
- ——
- 波田野さんはなぜサンディーさんに、ラジオDJを始めいろいろと新しいことをやらせようとされたんでしょうね?
- Sandii
- あのころ波田野さんはそういうことすべてを、私が主人公のドキュメンタリーのように見ているとおっしゃっていて…。
- ——
- ?それはどういうことなのでしょう。
- Sandii
- それがね(笑)、その頃に波田野さんから伺ったのは、私をそういう世界に引き入れた上で、ハワイからやってきた心優しきフラガールがロックとドラッグに染まっていくドキュメンタリーを見ているつもりだからって。※1
- ——
- えー!それは…もしかしたらハワイの健康美女のようなサンディーさんを、アメリカン・ニュー・シネマとかフィルム・ノワールみたいなダークな世界にキャスティングして劇的なコントラストを作ってみたかったとか。
- Sandii
- ねえ?(笑)。
- ——
- それが本当だとすると、もはや面白がっているとしか思えませんが(笑)。
- Sandii
- ケミストリーを見たかっただけなのかしら(笑)?たぶん、わたしっていう日本の放送業界にとっては未知のエイリアンみたいな人材をイジって楽しむっていうか、「これはできないだろう」と思ってやらせてみたら「あ、できちゃったよ!」みたいな。もし、それだけユニークな素材として見ていただいていたのなら嬉しいね。それで「この子になにが向いているだろう」って試されたというか面白がられたというか(笑)。
- ——
- 実際にどんなことを試されたんですか?
- Sandii
- たとえば『昼のプレゼント』っていうNHKの番組にいきなり出ることになって「端唄(三味線の伴奏で短い曲を歌う純邦楽のジャンルの一つ)できる?」「え?端唄って…わたしが?」みたいな(笑)。あと、番組の企画で、歌手の双葉百合子さんからレッスンを受けたこともある。わたしそういうとき「はい。やります」って全部受けちゃうから。
- ——
- 新しい体験なんでもOKと。
- Sandii
- そうすると「じゃあ次はこれを」みたいに次々に未知のことをさせてくれるから、すっごい面白かった。ハワイにいたらそんなこと絶対に経験できなかったものね。
- ——
- それはそうですね(笑)。双葉さんと言えば「岸壁の母」が超有名ですが、その企画では浪曲かなにかのレッスンを?
- Sandii
- なにか謡曲、小唄だったかな。やったら意外とできてしまって、すごく楽しかったなあ。そう言えば、リック・ウェイクマンのインタビューのお仕事も、波田野さん経由でいただいたことがあって。
- ——
- なんとサンディーさんとプログレ!リックといえばイエスのキーボード奏者ですが、グループの初来日の時ですか?…いやそれだとサンディーさんが日本で落ち着く前になるはずだから、75年のソロ公演の時ですかね。
- Sandii
- たぶんその頃だと思う。わたしが英語を話せるから選ばれたということもあるかもしれませんね。彼の泊まっているホテルに波田野さんと一緒にインタビューに行きました。
- ——
- 以前にイエスについて日本のアーティストの方に取材した時に伺ったお話だと、リックさんはかなりのお喋りマシーンだということですが。
- Sandii
- そう!…そうか。私のときだけじゃなかったんだ。
- ——
- ええ。その方…まあぶっちゃけ鈴木さえ子さんですが…は大変なイエス・ファンで、その時の記憶だけでしゃべりますけれど、鈴木さんがたしか90年代にリックが何かで来日した時に会う機会があった時のエピソードがありまして。
- Sandii
- ほうほう。
- ——
- 実は諸事情によって不本意な形で発表されたらしいイエスのアルバムで『ユニオン』※2というのがあるんですが、リックは鈴木さんに「僕はね、このアルバムはこんなふうになるはずじゃなかったと思ってね。聴くと泣けちゃうから『オニオン』って呼んでるんだよ」って(笑)。
- Sandii
- あっはっは(笑)。ダジャレ?
- ——
- 玉ねぎで泣けちゃうという。まあオヤジ・ギャグ系ですよね。サンディーさんの時はいかがでしたか?
- Sandii
- ダジャレは出なかったけれど、ロック・ミュージックについてもう、語る語る!こっちが言葉を挟む暇がないくらいまくし立てておられましたよ。「ロックン・ロールは関係ない。ロック・ミュージックなんだ」って言っていたから、そのときはロックの元になったロックン・ロールやブルースにはあまり興味がなかったみたい。そしてそれを知らなかったトンチンカンなわたしが居てね(笑)、ちょうどブルースやルーツ・ロックに興味津々だったからそういう話を聞こう!と思って行ったのにっていう。でもでっかいことを語るだけでなく、人間のオーラも大きな人でしたよ。
 リック・ウェイクマン『地底探検』1974年発表/19世紀に書かれ、たびたび映画化もされた有名なSF冒険小説からモチーフをとったコンセプト・アルバム。英国フェスティヴァル・ホールでオーケストラ、合唱団と自身のバンドが共演したコンサートをライヴ録音したもので、クラシカルかつ派手なキーボード・プレイでドラマチックに盛り上げるリック独特のスタイルが成功してかなり売れた1枚。75年初頭にこのアルバムを引っさげた来日公演を行っているので、今回の話に出てきたサンディーのインタビューはそのときのものではないかと思われる。
リック・ウェイクマン『地底探検』1974年発表/19世紀に書かれ、たびたび映画化もされた有名なSF冒険小説からモチーフをとったコンセプト・アルバム。英国フェスティヴァル・ホールでオーケストラ、合唱団と自身のバンドが共演したコンサートをライヴ録音したもので、クラシカルかつ派手なキーボード・プレイでドラマチックに盛り上げるリック独特のスタイルが成功してかなり売れた1枚。75年初頭にこのアルバムを引っさげた来日公演を行っているので、今回の話に出てきたサンディーのインタビューはそのときのものではないかと思われる。- ——
- 実際の体も190センチくらいあってデカいですしね(笑)。それにしてもリック・ウェイクマンとは。私はイエスも彼のソロも好きなんで一通り聴いていますが、いかにもクラシック・ルーツの人というか、なんかサンディーさんとは音楽的接点が希薄なような。
- Sandii
- そうね。でもわたしは面白がっていたけれどね。まあ、このことに限らず波田野さんが私にいろいろな異種ジャンルの刺激的な方々をぶつけたり、やったことのない分野の仕事をさせていただいたりして、自分の幅を広げてスキルを吸収できたと思う。「若いこだま」のDJも夢中でやっていただけだけれど、あれがなかったらご縁がなかったような人たちといっぱい出会えて自分が進む方向にもいい影響があった。
- ——
- 今回はその波田野さんに裏付けのためにいろいろ当時のことを伺ってみたのですが、あの頃は富ヶ谷(渋谷区)に業界人やタレント、アーティストの溜まり場があって、そこの人たちを中心にサンディーさんのファン・クラブみたいなものがあったとか。
- Sandii
- ファン・クラブっていうか応援してくれる常連さんみたいな。収録現場に来て「サンディー!」って掛け声を出してくださるとか(笑)。
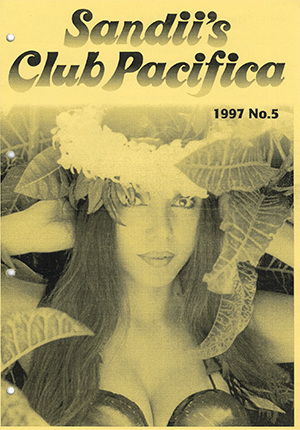
サンディーのファン・クラブ「Club Pacifica」の皆さまが
作ってくださっていた会報誌。
- ——
- なるほど。応援団ですね。それとですね、その頃サンディーさんは赤坂のクラブで弾き語りをやっていたんじゃないかな、と証言されていましたが本当ですか?だんだんバラエティ番組のタレコミ・コーナーのような流れになってきましたが(笑)。
- Sandii
- えー!それはどうかなぁ。たぶん日本のクラブとかでは弾き語りはやっていないと思うけれど…。もしかしたらこの間お話しした、テレビの歌謡番組の打ち上げの席で赤坂のピアノ・バーで弾き語りをした件のことをおっしゃっているんじゃないかな。
- ——
- この間伺った件。そのころはサンディーさん自らギターも弾きながら歌うこともあったという。
- Sandii
- 昔、弾き語りをやっていた自分がいたっていうのが今思うと信じられないけれど、あの頃は普通にやっていましたね。その後に、ウクレレ弾きながら歌う立場でありながら、いい奏者の方々といっぱい出会えて歌に専念するようになりました。そうすると、不思議なもので歌に特化することで出てくる新しい自分というものに出会えるんですね。
- ——
- そうか。専念することで歌手サンディーが本格的に始まるわけですね。
- Sandii
- そう。100%歌に集中できるようになったことで歌い手としての軸が開くっていうかな。歌に関してのエネルギー体が大きくなる感触がありました。歌うっていう一方向に向き合うことで、よりきめ細やかに感情表現する余裕が出るんだね。それに、昔から1人でやるより「旅は道連れ」で誰かと一緒に組んでやる方が好きで、力も発揮できる気がするんです。
- ——
- いわゆる音楽のケミストリーというものがよく働く。
- Sandii
- そのほうがわたしには合っているかなって。音楽は直感で相手を選ぶ力を高めてくれるでしょう?
- ——
- あ、そこはサンディー語っぽいのでもう少しご説明をお願いいたします。子供に噛んで含めるようにして言い聞かせる感じで。
- Sandii
- (笑)。わたしの経験だと、その人が出す音を聞くと自分との相性がわかるというかな。特に歌や声は人格が出るものだからパッと生身の自分が出ちゃうのね。それで「この人とわたしはすごく合う!」とか「ちょっと道が違うかな?」っていうのがはっきりわかると思うの。それと、声は自分の感情、感覚のダイレクトな表現になるから、商品性はいちおう別にして、声を聴くとそれがアートとして成立しているかがすぐわかる。そういうことを言いたかったんだけど…今度はわかったかな?
- ——
- はい。噛んで含められて頭に栄養が行き渡ったようです(笑)。楽器演奏もですけれど、たしかに声は特にそういうところありますよね。それで以前伺ったように、その弾き語りの場にいた坂本九さんが感心してサンディーさんにNHKのオーディションを受けさせたというエピソードがあって、専業歌手・サンディー誕生につながっていくわけですね。あ、そういえば、そのオーディションのときに歌われた曲を伺ってませんでしたね。
- Sandii
- 憶えてない(笑)。
- ——
- ははあ。では当日のことで憶えていることというと?
- Sandii
- 九さんがリムジンで家まで迎えにきたところから、顔パスで一緒に局内に入って審査するスタジオまで行ったところまでの全部がまるで映画の中にいるみたいで、ずっとドキドキしていたのを憶えてる。なにかもう“大型新人”的に押し出されている雰囲気は感じていたけれど。
- ——
- なるほど。それでこれも波田野さんによれば、当時のNHKオーディションというのはひとつの壁で、自分流にユニークな歌い方をするニュー・ミュージック系の方々は最初みんな落ちたと。なにしろ審査員が藤山一郎さんのような昭和初期の名だたる歌手の方とかで、朗々と歌われる正統派の重鎮ですから、その価値観に合う歌唱じゃないとなかなか受からない。
- Sandii
- そうだったの?もうどなたが審査員でとか憶えていない。それくらい私が上がってたんじゃないかなあ。
- ——
- そんな中サンディーさんが一発で受かったのは、やっぱりスタンダードに技術のある歌い手だったんでしょうね。
- Sandii
- わたしにしてみれば、すごく楽しい経験をさせていただいたなあって。ポテンシャルを見出してくださった先達たちに感謝です。波田野さん、九ちゃん。あと萩原さんっていう波田野さんの上司だったとても先見の明と実力のある方がいらしてね…。
- ——
- はい。波田野さんからも伺いましたが、サンディーさんにとって大変重要な方だったようですね。今度またお話を伺っておきたいと思いますので、その時にサンディーさんとの関わりを詳しく教えてください。ところで、そのころに活躍された同期の歌手の皆さんというと、どなたが印象的だったでしょうか?
- Sandii
- そうですね…亡くなってしまわれたけれど(2016年)、りりィさん。いちどNHKのスタジオで彼女と対談したことがあるんです。その場にはさっき話に出た後援会の人たちが集結しちゃってね。結局は対談というか、なんだかみんなでワーワーいろいろな話題で盛り上がっていって、なんというかNHKっぽくないフリーでアナーキーな討論会のようなイベントになったんです。すごく面白かった。
- ——
- 管理されていない感じが伝わってきますね。
- Sandii
- あの頃のメディアにはまだ、かなり自由なところがあったからね。
- ——
- サンディーさんは、アーティストとしてのりりィさんをどのように捉えていらっしゃるんですか?
- Sandii
- 私の感性で言えば、りりィさんはナチュラルな人ですね。もちろんソング・ライティングの才能もすごくあった。デビューは私より何年か早い先輩なんですけれど、いい意味でヒッピー的というか自分に正直にしか生きられない方という印象が強くあります。少なくても、私が接した限りではいかにも芸能人という方ではなかった。
- ——
- 自分が中学生くらいの時に「私は泣いています」がヒットしてよく流れていましたが。
- Sandii
- その「私は泣いています」というタイトルや歌詞、それとあの独特の歌い回しは彼女にしか書けない、歌えないと思うんです。他の人がやってもきっと仮着みたいになってしまって、彼女のあのハスキーで繊細な声があってこそ成立する詞の世界がある。
 りりィ『私は泣いています』1974年発表/りりィ最大のヒット曲で、100万枚を超える売り上げがあったという。「私は泣いています、ベッドの上で」というインパクトある歌い出しは全国に広まり当時は子供でも口ずさむほどだったので、最近で言えば「パプリカ」に近いテイストのヒット曲だったと言えるだろう(違うか…)。それと同時に従来の流行歌手にはなかった彼女の個性が滲み出た独特の節回しの歌唱やワイルドかつボヘミアンな佇まいは新たなアイドル像を生み出し、日本のポップ・ミュージックの幅を音楽性とキャラクター・スタイルの両面で広げた(これは本当な気がする)
りりィ『私は泣いています』1974年発表/りりィ最大のヒット曲で、100万枚を超える売り上げがあったという。「私は泣いています、ベッドの上で」というインパクトある歌い出しは全国に広まり当時は子供でも口ずさむほどだったので、最近で言えば「パプリカ」に近いテイストのヒット曲だったと言えるだろう(違うか…)。それと同時に従来の流行歌手にはなかった彼女の個性が滲み出た独特の節回しの歌唱やワイルドかつボヘミアンな佇まいは新たなアイドル像を生み出し、日本のポップ・ミュージックの幅を音楽性とキャラクター・スタイルの両面で広げた(これは本当な気がする)- ——
- 海外で似ているシンガー・ソングライターもいませんよね。日本的というか東洋的な情緒があって。
- Sandii
- そうね。わたしの感覚だと、あえて似ているイメージの歌手を探せばシルヴィー・ヴァルタンみたいなフリー・スピリットのワイルド・ガールのイメージかな?それまで数多くいた芸能人歌手には作れない新しい物を供給してくれる人という感じ。
- ——
- それはよくわかる感じがします。あの頃は「ニュー・ミュージック」と呼ばれる自作自演の方々がわっと世に出てきて、それまで自分が聴いていた歌謡曲ポップスとは歌い方にしても歌のテーマにしても全然違うなと。なにか目が覚めるような感じがしました。
- Sandii
- いちおう芸能界に居るけれどそこから脱皮している新鮮な風という雰囲気があって。作り上げられたアイドルと違うっていうのがすぐ受け手に伝わって、あれだけ人気が出たんじゃないかな。特に、ざらついているけれどコアはフェミニンでガラスのハート、みたいなアンビバレンツな繊細さが彼女の個性だよね。
- ——
- なにか心の傷みたいなものがよく歌のテーマになるというか。
- Sandii
- 痛い思いをアートにするギフト(才能)があった。ご本人はきついだろうなあ…。あと、ジョニ・ミッチェル的な感じで、恋愛と音楽性の変遷の関係という回路もあるのかしら。恋にまつわる生の感情を正直な言葉で書いて、そのままの肉声で届ける。
- ——
- ジョニ・ミッチェルは実生活での恋愛体験が歌とパラレルになっている感じはありますかね。自分が恋していると、その男性を野生のコヨーテに例える歌を書くとか。
- Sandii
- だから彼女は大変だったと思うのよ。私生活が歌になっているところがあって。
- ——
- 晩年のころもお付き合いがあったのですか?
- Sandii
- 実はね、波田野さんからのご提案でラ・ママか屋根裏※3でサンディー&りりィの共演リサイタルをやるという話が持ち上がっていてね。わたしたち二人のスケジュール調整している間に亡くなってしまわれて…。
- ——
- そんな話が!もしご存命なら今の時代、まだまだ活躍の場が広がったことでしょう。
- Sandii
- 私もそう思います。とても残念でした。でもまだこの世にいらっしゃるような感覚があってしょうがないのよね…。
- ——
- バイバイ・セッションっていうりりィさんのバック・バンドも日本のロックの基礎を作った名手揃いだったし、いろいろな意味で歴史に残る方でしたね。ほかにも同世代で気になる方というか、印象にある方というと?
- Sandii
- そういうキツめのイメージの個性だと、カルメン・マキちゃんも独特だったわね。
(次回に続く)
- この記憶はその後の取材で、波田野氏ご本人によって大筋裏付けられた。
- 『Union』。邦題は『結晶』。91年発表で、当時二つのグループに分裂してそれぞれのアルバムを作っていたものを、メンバー間の和解に伴うレコード会社の要請によって無理やり一つにまとめてイエス名義のアルバムにした、という事情があるようだ。
- ラ・ママ(渋谷・La Mama)か屋根裏/どちらも東京・渋谷の老舗のライヴ・ハウス。後者は移転や復活を経て2013年に閉店。
 イラスト:田丸浩史
イラスト:田丸浩史田山三樹 (ライター/編集)
編著に『NICE AGE YMOとその時代 1978-1984』(シンコーミュージック・エンターテイメント)、編集担当コミック単行本に『ディア・ダイアリー』(多田由美)など。最新編集担当本は『よりぬきヒロシさん 気まずいの以外全部出し』(田丸浩史)。サンディーが80年代中頃まで在籍したアルファ・レコードについての読み物『アルファの宴』を『レコード・コレクターズ』誌で連載していた。







